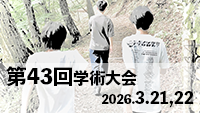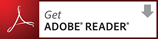当学会について

 2025年度から、日本集団精神療法学会の理事長を務めることになりました岡島美朗です。
2025年度から、日本集団精神療法学会の理事長を務めることになりました岡島美朗です。
学会と、集団精神療法について少しご紹介したいと思います。
日本集団精神療法学会は、1983年に設立され、40年以上にわたって活動してきました。
学会の目的は「集団精神療法に関する理論と実践の発展・深化」とされていますが、現在までのところ、理論よりは実践と教育に活動の重点があります。
主な事業としては年1回の学術大会と大会前日のプレコングレス、さらにやはり年1回の集団精神療法の研修会があります。
研修会は全国各地で開催され、会員だけでなく、多くの方にご参加いただき、集団精神療法に触れていただいています。また、学会が国際集団精神療法・集団過程学会(IAGP)の機関会員となっており、国際的な交流も行っています。
ところで、集団精神療法とはどのようなものか、ご存じでしょうか。アメリカの映画で精神科病院が描かれる際、しばしばグループ場面がでてくるのでそのイメージをお持ちの方もおられるかもしれません。
精神医療を題材としたものとしては古典的な映画「カッコーの巣の上で」では、厳格な師長が司会をするグループが出てきます。グループでは、主に師長が問いかけ、それぞれの患者がそれに答えて、さらに師長が評価する、というやりとりが続きます。
そこでは医療者と患者の役割ははっきりと区別され、また普段は個別に行っている精神的ケアや指導を集団で行っているように見えます。映画の描写はあまりに極端ですが、情報伝達やスキルの指導を目的としたグループは日本の医療現場でも多く行われています。
精神科では心理教育ミーティングや集団SST、精神科以外でも糖尿病教室やプレパパ・ママクラスなどが挙げられるでしょう。医療以外の領域でも心理教育的なアプローチを集団で行っているのは、日常的なことかもしれません。しかし、集団精神療法の有効性、そして魅力はそれにとどまるものではありません。
当学会が大切にしている、集団精神療法の基本となる要素、それを最大公約数的にいえば、「集団力動」ということになります。力動的な見方とは、心の動きを物理的な力のようにとらえて理解することですが、グループの中に入り、自分と他のメンバーに生じる様々な力動を体験し、それがどういうものであるか理解しようとするのが集団精神療法の目標です。
最初にグループに入った時の不安や緊張、自分の発言に同意してもらえた時の安心感、他のメンバーの発言に刺激されて思い起こされる記憶など、グループのなかではさまざまな気持ちの動きが体験されます。そうした心の動きは、普段の人間関係のなかでも生じていて、その人の行動の影響を与えているかもしれません。また、グループ全体を見る視点を取れば、ある人の強引な意見に対して反対するメンバーが結束したり、沈黙が続くとセラピストに何とか打開してほしいと期待する雰囲気が強まったりするといった力動が見えることもあるでしょう。
グループのなかには心理教育や集団認知行動療法のように、特定の課題に応えるようプログラムされているものもありますが、その課題を遂行する際にも力動は必ず生じています。力動に目を向け、言葉にしようと努力することが、治療としての集団精神療法の営みなのです。自分の心の動きを見つめるというのはつらいことだと思われるかもしれませんが、共通の目標をもったグループは暖かいものです。グループに所属した経験が、それからの人生に一歩を踏み出す勇気を与えていることも少なくありません。
もちろん、こうした集団力動は治療グループの中でだけ起きているわけではありません。家庭、学校、職場、趣味のサークル、自治会、ボランティア活動など、われわれは日々さまざまな集団に属しながら生きていますが、それぞれの集団のなかでもさまざまな力動が生じているはずです。力動的グループの視点をもつと、その集団で何が起きているかがわかり、それまで解決が難しかった問題にうまく対処できるかもしれません。力動的視点を持って組織運営に助言することを組織コンサルテーションと呼びますが、当学会はこの領域にも取り組んでいきたいと考えています。
少しグループに興味がわいてきましたか?ちょっと勉強してみようかな、と思われたら、学会関連の研修会・研究会に参加してみてください。グループを勉強するためには、自分がメンバーになってグループを体験すること(一般に体験グループと呼ばれています)がとても重要です。ホームページには学会が主催する研修会のほか、学会メンバーが企画する研究会の情報が数多く掲載されていて、それらの研究会・研修会では体験グループや事例検討が活発に行われています。
ぜひいっしょに、グループを体験し、勉強していきましょう。
学会役員及び代議員
| 理事長 | 岡島 美朗 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 副理事長 | 西村 馨 | ||||
| 理事 | 梶本 浩史 | 鎌田 明日香 | 菊地 寿奈美 | 白柿 綾 | 神宮 京子 |
| 菅 武史 | 関 百合 | 高橋 馨 | 多喜田 恵子 | 武井 麻子 | |
| 二之宮 正人 | 林 公輔 | 藤澤 美穂 | |||
| 監事 | 田辺 等 | 長谷川 麻弓 | |||
| 代議員(地区別) | 北海道地区 | 鎌田 明日香 | 小山 芳明 | 山本 創 | |
| 東北地区 | 稲村 茂 | 藤澤 美穂 | |||
| 関東地区 | 大島 朗生 | 岡島 美朗 | 梶本 浩史 | 小宮 敬子 | |
| 桜庭 拓郎 | 柴田 応介 | 神宮 京子 | 関 百合 | ||
| 高橋 馨 | 武井 麻子 | 藤堂 信枝 | 徳丸 享 | ||
| 西村 馨 | 林 公輔 | 袰岩 秀章 | |||
| 甲信越・北陸地区 | 奥田 宏 | ||||
| 東海地区 | 多喜田 恵子 | ||||
| 近畿地区 | 菊地 寿奈美 | 岸 信之 | 高 富栄 | 宮城 崇史 | |
| 中国地区 | 岡﨑 翼 | 菅 武史 | |||
| 四国地区 | 白柿 綾 | ||||
| 九州・沖縄地区 | 坂口 信貴 | 二之宮 正人 | 堀川 公平 |
事業運営組織
| 事務局 | 事務局長 | 高橋 馨 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 桜庭 拓郎 | |||||
| 会 計 | 多喜田 恵子 | 白柿 綾 | |||
| 編集委員会 | 委員長 | 林 公輔 | 副委員長 | 大橋 良枝 | |
| 大島 朗生 | 菊地 寿奈美 | 佐藤 幸江 | 柴田 応介 | ||
| 神宮 京子 | 藤堂 宗継 | 野中 稔 | 藤澤 希美 | ||
| 袰岩 秀章 | 松本 佳子 | ||||
| 事務局 | 片上 絵梨子 | ||||
| 教育研修委員会 | 委員長 | 関 百合 | 副委員長 | 加藤 隆弘 | 鎌田 明日香 |
| 地区委員 | 稲村 茂 | 岡島 美朗 | 奥田 宏 | 鎌田 明日香 | |
| 白柿 綾 | 菅 武史 | 多喜田 恵子 | 西村 馨 | ||
| 二之宮 正人 | 宮城 崇史 | ||||
| 職域委員 | 石川 見佳 | 小川 悠介 | 小野塚 美和 | 梶浦 麻琴 | |
| 加藤 裕介 | 加本 有希 | 川口 玲華 | 久保 浩明 | ||
| 黒江 美穂子 | 佐藤 裕宗 | 勢島 奏子 | 高橋 美紀 | ||
| 田口 明子 | 藤澤 希美 | 藤巻 純 | 松井 朋美 | ||
| 水野 高昌 | 山﨑 愛実 | 山﨑 圭実 | |||
| 事務局 | 卜部 裕介 | ||||
| 広報委員会 | 委員長 | 菅 武史 | 副委員長 | 野中 稔 | |
| 石川 健太 | 加藤 裕介 | 鎌田 明日香 | 高 玲児 | ||
| 廣瀬 真理 | 山野上 典子 | ||||
| 国際委員会 | 委員長 | 神宮 京子 | |||
| 大橋 良枝 | 前田 潤 | 水上真理子 | |||
| 渉外委員会 | 委員長 | 二之宮 正人 | |||
| 池田 望 | 大橋 良枝 | 桜庭 拓郎 | 藤澤 希美 | ||
| 松井 朋美 | 吉野 比呂子 | ||||
| 組織委員会 | 委員長 | 梶本 浩史 | 副委員長 | 徳丸 享 | |
| 石川 見佳 | 篠崎 絵里 | 徳田 幸絵 | 間嶋 崇宏 | ||
| 山野上 典子 | |||||
| 倫理委員会 | 委員長 | 菊地 寿奈美 | 副委員長 | 武井 麻子 | |
| 池田 望 | 小川 悠介 | 白柿 綾 | 松井 朋美 | ||
| 倫理問題審査委員会 | 委員長 | 菅 武史 | 副委員長 | 徳丸 享 | |
| 2025-2026年度研究倫理審査委員 | 卜部 裕介 | 大川 浩子 | 大橋 良枝 | 大森 眞澄 | 加藤 隆弘 |
| 加本 有希 | 高 富栄 | 桜庭 拓郎 | 佐藤 幸江 | 滝谷 七重 | |
| 藤澤 美穂 | 藤巻 加奈子 | 松尾 真規子 | 水野 高昌 | 宮城 崇史 | |
| 行成 裕一郎 | |||||
| 相互支援委員会 | 委員長 | 藤澤 美穂 | |||
| 安部 康代 | 高 富栄 | 髙林 健示 | 長友 敦子 | ||
| 橋本 明宏 | 針生 江美 | 藤 信子 | 山本 創 |
その他のワーキンググループ
| 実践倫理ワーキンググループ(倫理委員会) | 菊地 寿奈美 | 武井 麻子 | 池田 望 | 小川 悠介 |
|---|---|---|---|---|
| 加藤 祐介 | 嶋田 博之 | 白柿 綾 | 神宮 京子 | |
| 垰 雄士 | 高橋 裕子 | 松井 朋美 | ||
| 学会誌電子化ワーキンググループ(編集委員会) | 石川 健太 | 大橋 良枝 | 嶋田 博之 | 松本 佳子 |
| 倫理問題審査委員会規則ワーキンググループ(組織委員会/倫理委員会) | 大森 眞澄 | 高橋 裕子 | 徳丸 享 | 間嶋 崇宏 |
PDFファイルの閲覧にはAdobe社のAcrobatが必要です。
お持ちでない方は下のリンクよりAcrobatReader DC(無料)を入手して下さい。
定款・規程
- 一般社団法人 日本集団精神療法学会 定款(2024改定)(PDF)
- 入会規程(PDF)
- 会費規程(PDF)
- 名誉会員規程(PDF)
- 選挙規程(2024改定)(PDF)
- 個人情報保護方針(PDF)
- 特定個人情報取扱規程(PDF)
倫理
- 倫理綱領(2023年修正版)(PDF)
- 研究倫理ガイドライン(PDF)
- 研究倫理ガイドラインQ&A(PDF)
- 研究倫理審査チェックシート(PDF)
- 研究倫理審査申請書(WORD)
- 利益相反に関する指針(PDF)
- 「利益相反に関する指針」細則(PDF)
- 利益相反に関する指針及びその細則に関するFAQ(PDF)
- COI自己申告書 様式1:学会誌等 (PDF) (EXCEL)
- COI自己申告書(様式2:学術大会等発表用)(Excel)
- COI自己申告書(様式3:本会役員等用)(Excel)
- COI自己申告書(英語版 PDF)
学術誌関連
- 投稿規定・執筆規定(PDF)
- 学会誌分量等一覧(2019.3ver)(PDF)
- 論文・著者情報票(Word)
- 著作権の委任に関する同意書(例) (PDF) (Word)
- 著作権譲渡同意書 (PDF) (Word)
- Copyright Assignment Agreement (PDF) (Word)
- 著作物利用許諾申請書 (PDF) (Word)
- 著作物利用承諾願 (PDF) (Word)
教育研修関連
- 教育研修システム要項(PDF)
- グループサイコセラピスト申請―取得FAQ(PDF)
- キャンディデイト申込用紙(WORD)
- キャンディデイト研修記録用紙(PDF)
 キャンディデイト登録休止申請書(Word)
キャンディデイト登録休止申請書(Word)- SV認定申請書式(Word)
- SV再認定申請書式(Word)
 スーパーバイザー認定休止申請書(Word)
スーパーバイザー認定休止申請書(Word)- オンラインでグループを行うときの手引き(PDF)