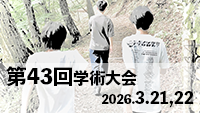「グループの中で、知らなかった私に出会う」
佐藤裕宗
藤澤さんからバトンを頂き、「グループと私」というJAGP43のテーマでコラムを書くことになり、あらためて自分が集団精神療法に出会ってからを振り返ってみました。
私は体験グループに出始めたばかりの頃、いつもグループで下ばかりを見ていました。特に沈黙の時は目線が下を向いてしまい、当時ほとんど何も話せず黙りっぱなしだった私は、参加している方々の足元ばかり眺めていました。どうすればいいかもわからず、沈黙のたびに下を向く私は、そのうち靴に思いを馳せてしまいます。「あの人は靴紐を違うものに変えているんだ」「あの人もこの人も同じメーカーの靴を履いてる。きっと良いメーカーなんだろうな」と、その場に集中できていませんでした。
そんな中、学会の研修会に参加したとき、体験グループで出た「緊張して足元ばかり見てしまいます」という言葉を聞いて、ハッとしたことを覚えています。私はそこで初めて、自分も同じ状況で、どうにもならず足元に逃げていたことに気がつきました。足元しか見られないことが辛かったし、不安だったことを自覚して、腑に落ちたような、自分自身の緊張や不安をちゃんと見ることができた、そんな体験でした。
それからは次第に靴への想いは薄れ、なんとなく外側に座っていた自分が、内側にだんだんと入っていくような、そんな感覚になりました。後に知ったのですが、当時の自分の反応は、グループ初心者にはよくあることのようでした。
その後もグループに出続けていた私は、ある時グループで自分の話をしたら、「怒っている」と言われました。私は昔から周囲に「怒らない人」と言われてきて、自分自身でもそうなんだと思って生きてきたため、怒りをあまり感じないとまで思っていました。だからか、そう言われて「いや、怒ってはいないですけど」と反射的に否定してしまいました。
しかし、何度か話をするたびに「怒っている」というフィードバックがたびたび返ってくるため、沈黙の中で考えてみると、話し出すと湧いてくる沸々とした熱があることに気づき、それが自分の怒りなんだと感じました。そしてそれと同時に、怒りを否定したい気持ちもあることがわかりました。
これについては多少時間がかかりましたが、「怒らない人」という自分のイメージとのギャップ、そういう人でいたいという自分の気持ちにも、その後に気づくことができました。これまで感じないようにしていた、蓋をしていた感情に気がつけたように思いました。そう考えて振り返ってみると、意外にも自分はたくさんの怒りを持っていることに気づき、ちゃんと怒りを感じられるんだなぁと思って、なんだか安心しました。今では自分で自分を「怒りの人」と自認しています。
思い起こすと色々ありますが、これまでの私の体験では、グループに出るたびに、自分のことに何かしら気づくこと、わかることがたくさんあって、良い体験と思えるものもあれば、辛い体験となるものもありました。しかし、それらの体験を振り返ると、グループの中で自分を考えるという時間は、私にとってとても貴重な体験でした。
そういった些細な自分への気づきを得られるから、今も私はグループに参加しているし、これからも参加し続けていくのだろうと思います。体験グループに参加し続けることは、本来の自分を取り戻すような、自分探しの旅のような、そんな気がしています。
今大会のテーマである「グループと私」について、大会長の林さんが「本大会では、他者とは違う私を知るための方法としての集団精神療法の可能性に注目したいと思います。」と述べていました。今大会が、参加される皆さんにとって、さまざまな体験を通して、他者とは違う自分を知り、自分だけでは気づけない自分に出会える場となるように、私も運営委員として微力ながら尽力したいと思います。
日本集団精神療法学会公式HPコラム 2026年1月
pdfファイルで読む →「グループの中で、知らなかった私に出会う」