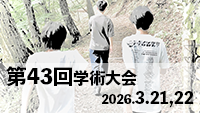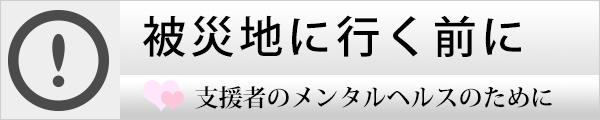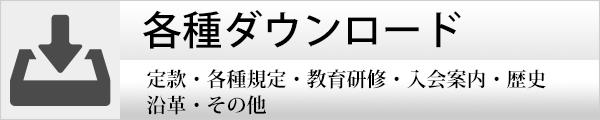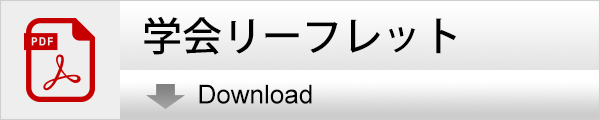リレーコラム「グループの立ち上げ」 No.10
与えられた機会で、それがグループとなるように
藤澤美穂
群馬の加藤祐介さんからバトンを引き継ぎました、岩手の藤澤美穂です。加藤さんとは2024年の第41回大会(高富栄大会長)の大会準備でご一緒したご縁がありバトンを渡していただいたものと理解しています。大会開催までの道のりを企画運営委員会というグループで共に進み、学会という大きなグループと相互作用していくプロセスは、私自身には2010年の第27回大会(宇田川一夫大会長)で経験した頃よりもよりダイナミックに感じられ、月日の重なりを実感することにもなりました。自分と時間軸にかかわる“縦”と、自分と周りにかかわる“横”とのつながりを感じられることが、グループに関わる上での醍醐味のひとつだと考えます。この縦横のつながりは、加藤さんのコラムにあったグループが「ある」からグループに「なる」へと変遷していくこととも関係するように思うところです。
さてグループの立ち上げというテーマで、私は日頃の業務が浮かびました。現在私は医療系大学の初年次教育の担当教員をしています。各学部教員はそれぞれの職能のプロフェッショナルで構成されていますが、私の部署は全学部の教養教育を担う役割のため、教員は数学や物理学、英語学などのそれぞれの学問分野の研究・教育者で構成されています。その中で対人援助専門職でもある教員は私(臨床心理士・公認心理師)を含め数名という少数派です。そういった部署の中で多職種連携教育に関わる科目の科目責任を担うよう命じられました。私の勤務校では現在、1・3・6年次(4年制学部は4年次)において学部横断的な多職種連携教育(IPE:Interprofessional Education)科目を開講しています。現代医療における専門性の高い知識かつ全人的医療への要請、ならびにそれらに基づく医療サービスの質向上の持続のため、異なる学部の学生が、同じ場所で共に学び、互いから学び合いながら、互いのことを学部/職種の垣根を越え学ぶ機会の確保という位置づけです。このような経緯・背景での1年生科目の責任者(リーダー)を担当することになったわけです。
初年次のこの科目は、アカデミックスキルの修得と、専門職間の連携意識とコミュニケーションスキルを高めるためのアクティブラーニングの両方が含まれ、それらの統合を図っていくという構成になっています。後者では、正解のない問いに対し複数学部混成の小グループでディスカッションをしながら結論に至り、そのプロセスの体験を通して他学部学生の専門性への関心と理解を深め、チーム医療の基盤づくりにつなげることを目指します。これらの小グループ作業に私の部署の二十数名の教員全員がテューターとして関与し、学生の主体的な学びと議論をサポートする体制をとります。
リーダーとしての私は、アカデミックスキル修得部分を担当する教員のグループ、アクティブラーニングの構成検討を担当する教員のグループ、テューターとして指導関与する部署教員全体のグループ、そして上級学年の多職種連携科目担当との協働連携という全学的位置づけのグループと、多層なグループに同時並行で関与する、そんな毎日を送っています。
この役割となったのは昨年からです。そして今まさにこれらのグループの一部として、またこれらのグループに向き合いながら、科目の歴史や経緯を踏まえながらも新たに求められることを取り入れ、また各グループ同士のつながりを意識しながら、奮闘しているところです。
多職種連携という点では、対人援助職ではない教員にとってはその実際をイメージしにくい事情があります。また各教員の背景、たとえば本学での在勤年数やアクティブラーニング教授経験、学生との距離感や指導方針など、様々な違いもあります。私自身はまずは、メンバーとなる担当者同士のグループが安全で心地よく、かつ創造性を発揮できるように、ということを心がけるところです。そして担当教員たちの雰囲気が学生にも伝わるだろうとも考え、学生が将来チーム医療を構成するメンバーとなったときの多職種連携イメージの一端をささやかでも担えるように、ということも意識しています。馴れ合いではなく、必要な意見や指摘をしながらも、互いを尊重し、力を合わせるというあり方の追求と言えるでしょうか。それらがうまく実現できるよう、グループと関わる自分自身を振り返り点検する日々です。
役割を担った個人の集合としてのグループが「ある」状態からグループに「なる」ことへの移行が可能となるように、そして組織として目標を共有しながら共に支え補いあえるチームに展開できるように——昨年からの新たな役割に臨む中で考えていることです。
次のバトンを、同じ東北の中でグループの視点にて取り組んでおられる方につなぎます。
日本集団精神療法学会公式HPコラム 2025年6月
pdfファイルで読む →与えられた機会で、それがグループとなるように