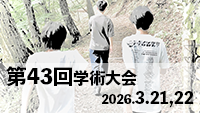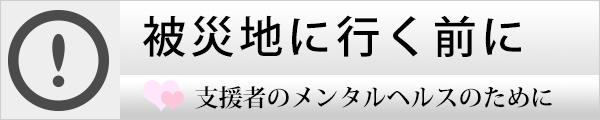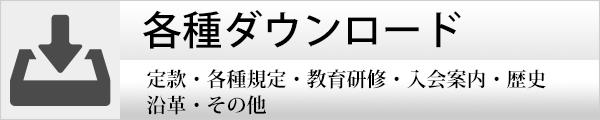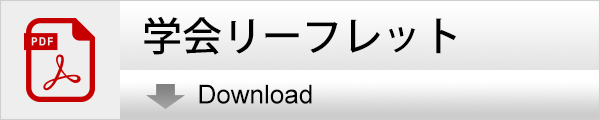リレーコラム「グループと私」No.1
第43回大会への、心構えのようなもの
髙橋馨
「タカハシさんみたいなバランサーが必要なんですよ」と、Aさんは日本酒のグラスを傾けながら言った。職場状況があまりに混沌としていて、かつての同僚数人に愚痴をこぼしていた時だ。その時はAさんの指摘を深く考えもせず、「ふぅん、そんなものかな」と刺身をつまみながら大層酒を飲んだので、この原稿を書くまでそんなことはすっかり忘れていた。バランサー?Aさんは、僕のどんなところをそう表現したのだろうか、コラムの原稿依頼が来てから、どうしてか頭によぎるようになった。そして妙なことに、つい先日上司に「いやー、タカハシくんがうまくバランスを保ってくれてるから助かるよ」みたいなことを言われた。職場でたまたま上司と二人になる時間があって、やはりこの時も日頃の状況をやや愚痴っぽく話していた時だ。どうも僕が愚痴っぽくなると、周りの人は「君はバランサーとしてよくやってくれてるよ!」みたいに僕のことを慰めて(励まして?)くれるみたいだ。
コンダクター(ファシリテーターとかリーダーとか言ったりする場合もある)の仕事は、グループに「水をさすこと」だと教わった。グループが盛り上がっているように見える時は、グループでは抱えきれないネガティブな何かが隠されていることが多くて、コンダクターの仕事はその隠された何かをみんなが見えるような形にして差し出すことにある。「みんなに見えているのに、みんなが見ようとしないものを見えるようにするのが、コンダクターだ」と言った人がいたけど、誰だったかな?精神科デイケアで言語のグループをしていて、グループが何か一つの話題に熱中した時に僕は「さっきの⚪︎⚪︎さんの発言はどうなったんだろう?」とか、「⚪︎⚪︎さんが立ち上がってどこか行ったね」とかよく言っていたのを思い出す。その時は「水をさそう」と意識していた訳ではなかったろうけど、そうすることでグループが現実感覚を取り戻し、全体のおさまりみたいなものが落ち着くことが多かったように記憶している。左右どちらかに傾きかけた船が、ちょうど安定するみたいに。
僕は今、児童相談所で児童福祉司という仕事をしている。児童福祉司、と聞くと「グループなんて関係ないじゃないか」と思う方もおられると思うけど、実は全然そんなことはなくて、そもそも児童福祉司が相手にするのは基本的には家族というグループなわけで、グループを見る目、というか関係性や集団力動の理解というものを自分の中に備えておいた方が、きっとずっと仕事がしやすくなるのではないかと個人的には思っている。ここでその詳細に踏み込むことはしないけれど、またきちんとした形でどこかで「児童福祉×グループ」について書いてみようかなと(ちょっと)思っている。ちなみに、この業界に入ってすぐの頃に僕は、「この仕事はバランスをとる仕事だよ」と先輩から教わった。子どもと親、とか子どもが入所している施設と親、とか時には子どものことで困っているご夫婦の間とかを取り持ちつつ、時にそれぞれに水をさしながら子どもが安心して生活できるように支援する仕事は、グループのコンダクターのようなものなのかも知れない。
「グループと私」をテーマにした第43回大会の準備をしつつ、僕はそんな風に考えている。
日本集団精神療法学会公式HPコラム 2025年9月
pdfファイルで読む →第43回大会への、心構えのようなもの