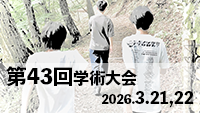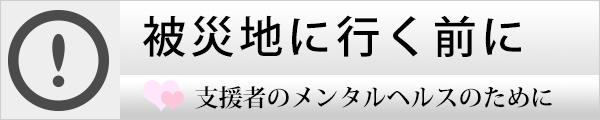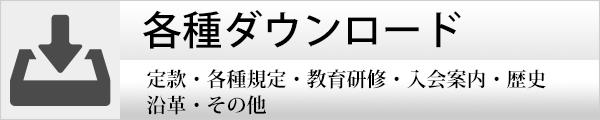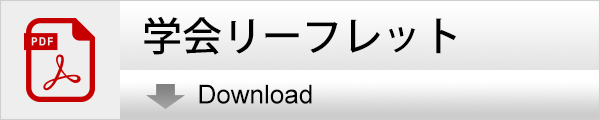リレーコラム「グループと私」No.3
グループで積み重ねてきたもの
岡田靖子
私は反抗期の塊だった高校時代、とにかく家族からも学校からも日本からも(?)自立したいと看護の道を選択、入学した学校ではなぜだかグループが多く…。卒業して看護師になって就職した精神科病院ではよくわからないままに病棟グループを行い、その後グループを勉強しようというよりも、グループの参加を続けようという感じで月一の体験グループに入りました。
グループでは、コンダクターやメンバーの方々を「あの人はおじいちゃん」「あの人はお母さん」と勝手に家族のイメージを押しつけてしまうことが多く、そしてグループが終わった帰り道ではなぜか自分の両親に電話をして安否を確認することが続きました。今思えば「グループの終わり」が家族の終わりのようで、ものすごく心細かったのだろうと思います。あんなに家族という塊から逃げたかったのに。
高校生の時は、大人になったら海外でバリバリ働いてなんて、そんな私って強くて素敵って妄想していたのに、実際にはグループが終わっただけで、不安でさみしくなって、親に電話する自分。「元気?生きてる?今日グループしてね(内容は言わないけれど)。元気だったらいいの。」と高飛車で一方的で内容もよくわからない娘の報告電話によく付き合ってくれたものだと思います。
現在は生まれ育った下町で訪問看護をしています。日本からも飛び出して、というあの頃の将来の自分像はどこに行ったのでしょうか。
訪問看護では、障害がある家族だったり、終末期だったり、色々な危機に直面している家族の中に入ります。もちろん身寄りのない一人暮らしの家にも。多くの場合、その家庭の事情やルールを「押し付けてくる」のではなく「分かっているのが当たり前」で対応が進んでいきます。問題解決なんて簡単にできません。ただただ、なんだか巻き込まれて色々やって訪問時間が終わります。でも、「次はいつ?」「世話になった」と言って待っていてくれる人が多いので、その時の関りはたぶんケア的な何かになっていることが多いのでしょう。
そして訪問を終えて家の玄関を出て、自然と膝や手が震えていたり、「もうやめたい」と口に出している自分に気づきます。孤独でさみしい、貧しい、辛い、痛い、怖い、そんな感情や、自分や家族の死の場面が否応なしに流れ込んでくるのに気づきます。たぶん、気づけるようになったのは、グループに参加し続けて、自分の体験を話していたから。そして、いたわりの言葉をかけられた場面や一緒に笑い飛ばしてくれた場面がふっと芽を出して、「さて、次も頑張るか」という気持ちになります。グループで積み重ねた体験が、家族や人に寄り添い続けるのはとても辛くて厳しい時もあるということを自覚しながらも、積極的に関心を持ち関り続けていくエネルギーの源になっているのを感じます。
慶應義塾大学三田キャンパスで行われる第43回学術大会。これまでの訪問看護とグループの体験で培った経験を活かして、参加される皆様がより自分を探求できるように、会場づくりを頑張りたいと思います。
日本集団精神療法学会公式HPコラム 2025年11月
pdfファイルで読む →グループで積み重ねてきたもの