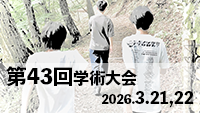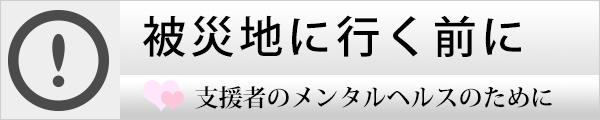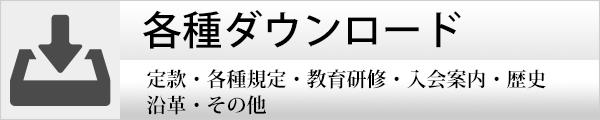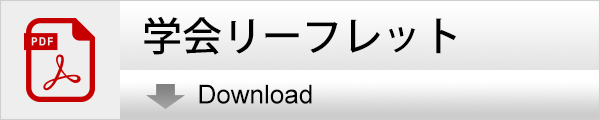リレーコラム「グループの立ち上げ」 No.09
「グループが生まれたとき」
加藤祐介
吉沢さんからバトンを引き継ぎました、群馬の加藤です。まさかリレーコラムの運営を担っている広報委員の私にバトンが届くとは、まったく予想していなかったのですが、改めて私も会員の一人なのだと感じられて、うれしい気持ちになりました。
さて、改めまして、みなさま、第42回学術大会、大変お疲れ様でした。当日参加された方、諸事情で参加できなかった方を含め、2日間(ある人は3日間、祝日を入れると4日間かも…)で、さまざまな体験をなさったのではないかと想像します。私は2年連続の運営委員として、大会の運営に関わらせていただきましたが、同じ「運営委員会」という名前の組織でも、その雰囲気や進め方は大会ごとに大きく異なっており、その違いを直に体験することで、多くのことを学べました。
大会のシンポジウムでも話題になりましたが、グループはそこに「ある」ものです。共通の目的を持った人が集まれば、すでにそこにはグループが生まれているといえるでしょう。今回、大会の準備にあたる運営委員会、そして当日のワークショップ、一般演題、事例検討、シンポジウムなどのグループという枠組みは、すでにそこに「ある」もので、私はそのグループに加わり、特定の役割を担ったにすぎません。しかし、それは今回の大会テーマである、グループが「生まれる」という体験とは、少し違うような感じがしました。では、グループが「生まれる」とはいったいどのようなことを指しているのでしょう?最初は、グループを運営しコンダクトする側の視点から、言い換えれば群衆や集団といった人々の集まりをグループ(集団精神療法)として機能させようとする専門家の視点から考えていましたが、大会を通して、参加者(グループメンバー)の視点からも「グループが生まれるとき」とはどういうことなのだろうか?と考えることができました。
運営委員だけでなく、一般演題、自主企画ワークショップなどのプログラムも、毎年同じような目的や枠組みを持ったグループといえるでしょう。しかし、私には、その年ごとに大きく違ったものとして体験されました。この違いについて考えると、グループがそこに「ある」だけでなく、その地域や、コンダクターを含めたグループに参加している人たちの関係性など様々な影響を受けながら、その枠組みが唯一無二の個性を持ったグループとして独自に成長・発展・変化していくプロセスがあるように思います。グループが「ある」と対比すると、これはグループに「なる」と表現することができるかもしれません。
このグループに「なる」プロセスは、大会テーマ「グループが生まれるとき」と関係がありそうです。私にとってそれは、グループにいることが保証されている安心・安全・信頼に基づく感覚に近く、学術大会や教育研修への参加を続けることで育った部分が大きいように思います。グループで何らかの役割(運営委員や発表者、企画者など)を担ったことも影響しているでしょう。加えて、意見や感じ方の違いがあっても排除されず、互いの存在を認め、互いに学び合うことを本質としている本学会は、ただ参加したり、役割を担うだけでなく、自分から何かを発信することが求められます。自分が体験したことを、勇気を出して一生懸命に伝え、メンバーに耳を傾けてもらい、反応してもらう。この心をこめて「話す」「聴く」の両方が達成されたときに、安心・安全・信頼の感覚が育ち、そこに「ある」グループがグループに「なる」、つまり自分にとっての唯一無二のグループが生まれるのだと思います。
私は、今回の大会で、勇気を出して、グループの中で「話す」ことの重要さを感じました。運営委員会でも、大会内でも、勇気をもって自分の体験を話し、それを聞いてもらうことで、自分がグループの一員になれたと感じました。一般演題や自主企画ワークショップでは拙い実践の報告を聞いてもらい、シンポジウムでは「特権のある人しか話していない」と感じられたことを、残念な気持ちと共に発言しました。これらを聞いてもらった瞬間、その場が私にとってグループに「なった」、つまりグループが「生まれた」と感じられたのでした。
残念なことに、グループが「生まれた」と体験して、すぐに大会は終わりを迎えました。喪失感と隣り合わせでもあるのだなと思います。しかし、この経験は、私のこころに残っています。グループ体験を通して学んだ印象的なフレーズに「話せばなんとかなる」「グループの風景を持ち帰る(グループでの体験を取り入れ、内在化する)」があります。グループには、トップダウンで行われる教育や指導とは違う、豊かで能動的な学びがありますが、それを得るためには相応の代償が必要となります。私が考えるのは時間と勇気です。
このコラムをお引き受けした時にも、私の中で「グループが生まれた」と感じました。これはグループに所属してきた長い時間の中で、グループやメンバーのことを知り、勇気を出して発言して自分の存在を知ってもらえたこと、そして言葉を受け取ってもらえたこと、このような相互関係の積み重ねの中で体験されたものなのかもしれません。シンポジウムで話題になった「群盲象を評す」「プロセスを信頼する」「謙虚さと他者を尊重する」「特権」「終り」といったテーマからも、私は「安全」だから話すのではなく「安全」な場所を作るために言葉にするという、勇気をもってチャレンジする姿勢や態度の大切さを学びました。ですから、本学会は「特権」をもたない人にこそ、勇気をもって、その思いを発言・発信してもらえるような場所であってほしいと思います。言葉にすれば聞いてもらえるという「希望」をグループに抱いてもらえるよう、私もグループに関わっていきたいと強く思いました。
さて、紙面も残りわずかとなりました。相互に学び合うことのできるグループが一つでも多く生まれることを望みつつ、このコラムを閉じようと思います。意図したものではありませんが、リレーコラムは順調に列島横断を進めています。この流れに乗って、次は北に向けてバトンをつなぎたいと思います。
日本集団精神療法学会公式HPコラム 2025年5月
pdfファイルで読む →「グループが生まれたとき」